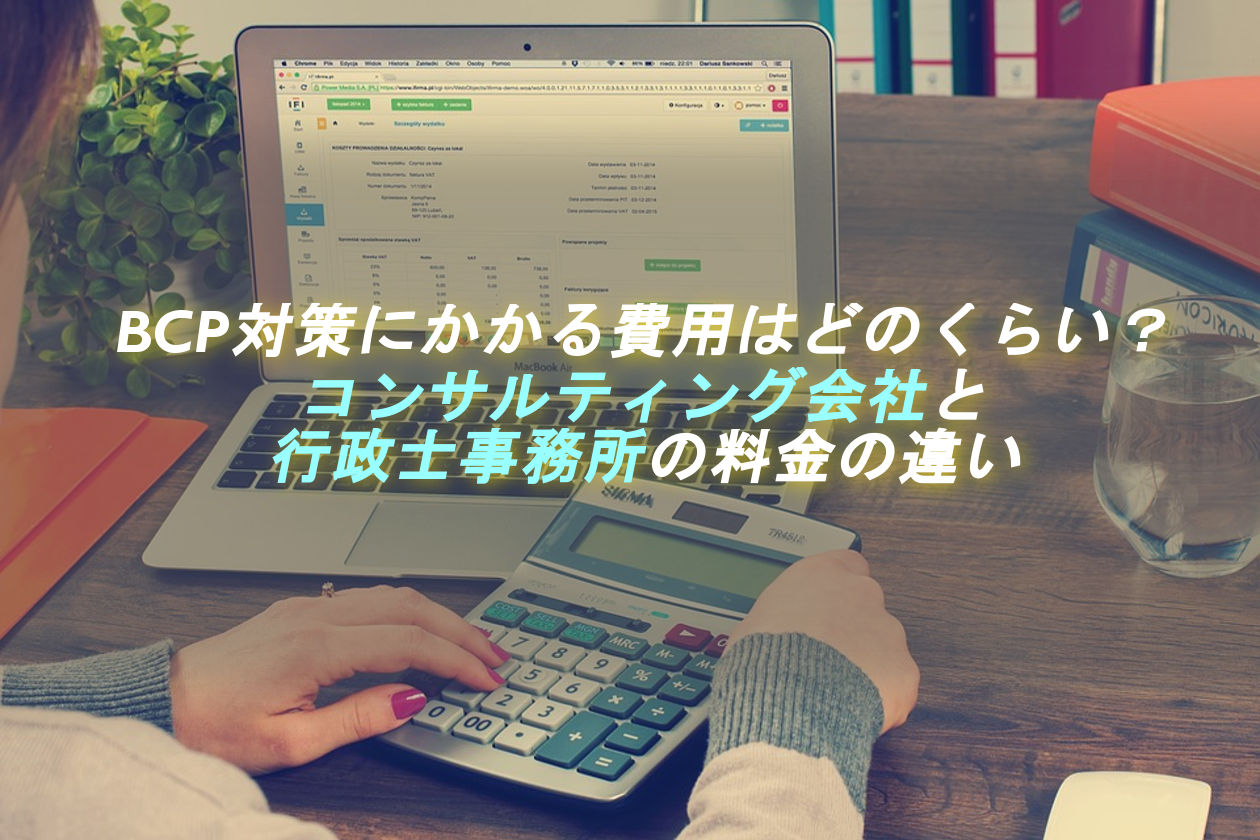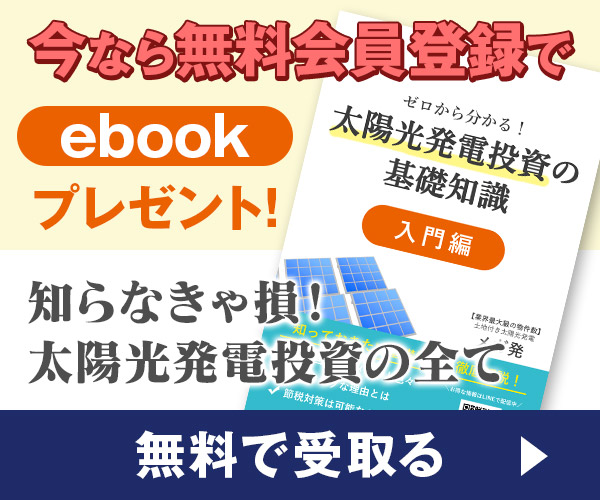BCP(事業継続計画)とは?その対策と蓄電池について
公開日:2019/04/12 | | カテゴリ:蓄電池と災害・停電・BCP対策について

最近目にする機会が増えたのがBCP(事業継続計画)という言葉です。とくに蓄電池を扱う際エネ関連のニュースメディアで、BCPやBCMSはよく登場します。さすがにBCP言葉の意味を全く知らない方はいないでしょうが、意味を調べても何となく腑に落ちない方も多いようです。
そこでこの記事では、これまであまり触れることのなかった「どのような経緯からBCPが始まった」のかも説明しています。この記事を読むことでBCPがより身近に感じられ、蓄電池との関係性も理解できるでしょう。
- BCPの概念はリスクマネジメントそのもの
- BCPの守備範囲は広く、大地震・ゲリラ豪雨などの自然災害から、感染症の蔓延、テロ等の事件など多岐に亘る
- BCPの役割は「事業を継続」「止まった事業の早期復旧」に集約される
- BCP策定の注意点は「中核事業の特典」「緊急時に提供できるサービスレベルを取引先と協議」「全従業員とBCP対策についてコニュニケーションを図」「蓄電池による電源確保」など
- BCPの重要性は「平常時から業務改善ができる」「「サプライチェーンとしての責任」「あらゆるステークホルダーへの社会的信頼の構築」「蓄電池による地域貢献」など
BCP(事業継続計画)とは?
まずはBCPとはいったいなんなのか、またどのような経緯でBCPという考え方が広がってきたかを説明していきます。
BCPの定義
BCP(事業継続計画)とは具体的にどういう意味を持つのでしょう?
まず、3文字で構成されるアルファベットは「Business(事業)、Continuity(継続)、Plan(計画)」から来ています。
なお、BCPは類義語としてBCRP(事業継続と復旧計画:Business Continuity & Resiliency Planning)とも呼ばれることもありますが、日本国内では一般的に「BCP」、あるいは単に「事業継続計画」と日本語読みが使われる場合もあります。
BCPとは以下のような定義となっています。
「大地震や台風・ゲリラ豪雨などの自然災害、感染症の蔓延、テロ等の事件、大事故、またこれらに起因するサプライチェーンの途絶、突発的な経営環境の変化など、不測に事態が発生しても、重要な業務を中断させない、また中断しても可能な限り短い期間で復旧するための方針、手順を示した計画のこと」
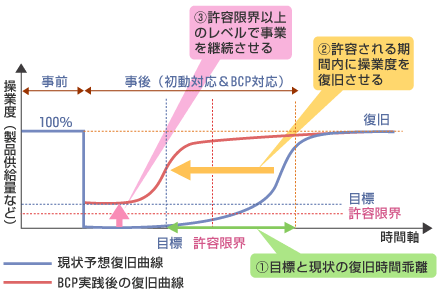
(事業継続計画の概念図「内閣府 防災情報のページより」)
このグラフに描かれている2種類の復旧曲線が示すように、簡単にいうとBCPの概念は「リスクマネジメントそのもの」だといえるでしょう。
企業等がBCPを平常時から準備しておけば、災害や事故発生直後における企業の操業性を維持でき、災害発生から復旧までに掛かる時間を短縮することができます。
また一企業や一工場が自助出来れば、自ずと共助・公助も促されます。ここにBCPの神髄があるのです。
BCPはどのような経緯で始まったか
蓄電池による電源確保の重要性と結び付ける機会が多いBCP「事業継続計画」は東日本大震災を契機に取り沙汰されるようになりました。
事実、現在のBCPの盛り上がりは2011年東日本大震災の反省と、同年7月から始まり3か月以上続いたタイの大洪水の教訓を経て生じたものです。 ところがBCPは、イギリスやアメリカなどの欧米ではすでに1970年代から議論されていますし、実は約10年遅れて日本でも1980年代に議論が始まっています。 つまりBCPは、少なくとも東日本大震災をきっかけに始まった概念ではなく、もっと前から普及プロセスがスタートしていました。
欧米では金融機関の情報システム導入が70年代から始まりました。それを受けてシステム停止に対する対応策が検討されるようになります。 そして80年代に入るとBCPの前身とも言うべき「コンティンジェンシープラン:Contingency Plan(不測事態対応計画)」が制定され、火災、地震、水害、竜巻、暴動、テロなどへと対応が多用性を見せだします。
このためアメリカでのBCPは自然災害を原因にしたものもありますが、金融機関のシステム障害や例えば全米を震撼させた「タイレノール事件」(1982年、1986年)などの毒物混入、あるいは「世界同時多発テロ」などを端緒として広がっています。
とくに「タイレノール事件」でジョンソン・エンド・ジョンソン社は、僅か2ヶ月で事件前の売り上げの8割を回復させています。まさにBCPの早期復旧の精神を現実化した典型的事例です。
一方、国内に目を向けると、日本では「電子計算機システム安全対策基準」(通産省)が1977年に制定され、1991年には「金融機関のコンピュータシステムの安全対策基準」(金融情報システムセンター)が出来ています。
ただ初期のBCP対策は、欧米同様、金融機関等の情報システム部門に焦点を当てたものがほとんどで、企業の製品やサービスの供給を継続させる全社的な行動指針などは、一切うたわれていません。
これが2000年代になると「国際会計基準」が導入され、日本においても「事業等のリスク」が取り上げられます。そしてBCP対策が本格的に認識され始め、2004年の中越地震の際、被災した一部の企業から「事業継続計画」への関心が高まりを見せます。
その後日本でのBCP対策はやや下火となりましたが、静かにBCP対策を行っていた企業は、東日本大震災でBCP対策の実効性を目の当たりにします。
このような経緯から、BCPがメディアでも取り上げら始めたのは、欧米では1998年ごろから、日本では2005年前後だと言われているのです。
日本国内でのBCPの広がり
ところでBCPの普及や認知はどの程度進んでいるのでしょうか。
2016年には大企業全体では60%、中小企業では30%の普及率を示しました。これに策定中の企業を含めると、大企業全体では75%、中小企業では42%だったようです。 2024年現在では大企業のほとんどが普及や認知に努めており、中小企業においても順調に波及しているとみられています。
どういった対策があるのか?
BCPにはどういった対策が盛り込まれているかを具体的に見ていきます。
BCPと防災マニュアルとの違い
BCP(事業継続計画)対策に入る前に、BCPと防災マニュアルとの違いについて簡単に触れておきます。
防災マニュアル
災害発生時の初動や事前対策を定めた、人命の安全や資産の保全を最優先とする対策です。
BCP
災害をはじめとするさまざまな緊急事態発生時、初動や事前対策を含め、人命や資産を保護しながら事業の継続・復旧を目指す計画です。
つまりBCPは下記の2項目について、方法や手段が考えられています。
- 事業を継続する
- 止まった事業を早期に復旧する
BCPと防災マニュアルはよく似ていますが、BCPは防災を含みつつ、企業の事業継続や早期復旧に特化した対策だといえます。
BCP対策の策定方法
BCPは自由に策定して構いませんが、基本的にBCP策定には2つの方法があります。ひとつは企業が独自に策定するもの。もうひとつは「事業継続マネジメントシステム」に関する国際規格「ISO23001」を取得する方法です。
独自策定
書籍・ガイドライン等を参考に、マニュアル等を自作にする。また行政が提供するテンプレートを活用しても良いでしょうし、プロのコンサルタントに協力してもらうのも良いでしょう。また社員に防災士の免許を取得させ、彼をリーダーにBCPの独自策定を進めることもひとつの方法です。
国際規格「ISO23001」
ISO 22301は、BCMS(事業継続マネジメントシステム)の運用を定めており、もちろんBCPの策定にも使えます。
SO23001は次の3つの柱から出来ています。
- 事業の中断・阻害を引き起こす事象への組織的な対応策の構築・運用
- BCMSのパフォーマンスおよび有効性の監視・レビュー
- 継続的改善
SO23001の取得には手間やコストが掛かりますが、BCPの仕組みを外部に対してアピールできます。
BCP策定の注意点
それでは、BCP策定の注意点についてまとめておきます。
中核事業を特定する
すべての事業を平常通りに進めることは困難です。そのため、社内で優先して継続・復旧するべき中核事業を特定しておきます。
中核事業の目標復旧時間を決めておく
中核事業は会社の存続にも関わる大事な事業です。そのため、緊急時における目標復旧時間を決めておくことも忘れてはならないでしょう。また、その事業を遂行するために必要な資源(資産)がどのぐらい残すのかも、あらかじめ決めておきます。
緊急時に提供できるサービスのレベルを顧客と協議しておく
災害時や緊急時に提供できるサービスについて、あらかじめ顧客と打ち合わせしておくと安心です。
事業拠点の生産設備、仕入品調達等の代替策を用意しておく
これは前項にもつながることですが、生産設備や仕入れについての代替策も顧客と打ち合わせしておくと良いでしょう。
全ての従業員とBCP対策についてコニュニケーションを図る
これは、BCPでは全社的取り組みとして言及される部分ですが、従業員全員と社内で「事業継続」についての情報を共有しておくことは、言うまでもなくとても重要です。
演習と改善
BCP対策を作っても、実際に全社的に理解・トレーニングを進めておかなければ、宝の持ち腐れになってしまうでしょう。そのため年に1回でも社内演習を行い、BCP対策をブラッシュアップすることです。
こうした過程を「PDCAサイクル」と言います。PDCAとは、Plan(計画)・Do(実行)・Check(評価)・Action(改善)のこと。
蓄電池による電源確保
最後に蓄電池の重要性についても触れておきます。
東日本大震災を始めとする多くの自然災害で、停電が意外と簡単に起きること、そして停電になると復旧にも時間がかかることを学びました。それと同時に私たちの暮らしが、いかに電力に依存したものなのかも知りました。
じつは太陽光発電も、電力供給が途絶えると使い物になりません。そのため比較的新しいBCP対策では、蓄電池による緊急時の電源確保が進められ、中小企業でもいまや当たり前となっています。
はじめは自社の規模に見合った容量で十分です。まだ導入していない企業は蓄電池の準備を進めるべきでしょう
BCP対策の重要性
BCPの策定が近年盛んになったのは、国にとっても企業にとってもBCP対策が大きな便益をもたらすからです。
BCP対策の重要性の観点から見ていきましょう。
- 事前対策や代替案を用意できる
- 平常業務から経営改善が行える
- サプライチェーンとしての責任を果たせる
- 取引先や投資家への信頼
- 蓄電池による発電機能は地域貢献につながる
事前対策や代替案を用意できる
BCP対策は災害時・緊急時の事前対策や代替案を用意できます。平常時ほど落ち着いた判断が難しい災害時・緊急時に、BCP対策で取り決めた事前対策や代替案を流用できれば、心理的ダメージはかなり緩和され、次の対策や手立てを用意できるでしょう。
平常業務から経営改善が行える
BCP対策は密接に経営改善にもつながっています。平常時からBCP対策を行うことで、社内の経営改善も自然と促すことになります。
サプライチェーンとしての責任を果たせる
サプライチェーンとは製品の原材料・部品の調達から、製造、在庫管理、配送、販売、消費までの全体の一連の流れのこと指す物流用語で、日本語では「供給連鎖」といいます。
2011年に起こったタイ大洪水では多くの日本企業が被災し、商品の供給が思うように出来ませんでした。この時の反省からBCPの重要性を認識した日本企業の数は多いはず。BCP対策は、サプライチェーンとしての責任を果たすことにもつながります。
取引先や投資家への信頼
BCPを策定しておけば、取引先や投資家にも「この会社は緊急災害時でも商品の供給を行い、復旧にも短時間で対応できる」という安心感を与えます。
ステークホルダーに対するCSRの向上
企業は利益追及、法令尊守だけでなく、あらゆるステークホルダーの多様な要求に対して適切な対応を取る義務があります。BCPの策定はコンプアイアンスに続き、企業の新たな義務となっています。
蓄電池による発電機能は地域貢献につながる
大手企業で非常時の停電対策として、蓄電池による電源確保はいまやBCPの常識となっています。なぜなら蓄電池からの電力供給によって、業務の早期復旧が促されるからです。
またDCP(地域継続計画)という観点からも、蓄電池による電力インフラの提供は大きな意味を持っています。
小規模のオフィスで1週間ほどの復旧なら、小型の蓄電池で十分備えられるでしょう。また多くの電力を消費する工場などでは、太陽光発電を導入した蓄電システムを備えるところも多くなっています。
何れにしてもBCPと蓄電池による発電機能は、今後益々深まっていくことは確実です。
まとめ
最後にもう一度BCPについておさらいしておきましょう。
- BCPの概念はリスクマネジメントそのもの
- BCPの守備範囲は広く、大地震・ゲリラ豪雨などの自然災害から、感染症の蔓延、テロ等の事件など多岐に亘る
- BCPの役割は「事業を継続」「止まった事業の早期復旧」に集約される
- BCP策定の注意点は「中核事業の特典」「緊急時に提供できるサービスレベルを取引先と協議」「全従業員とBCP対策についてコニュニケーションを図」「蓄電池による電源確保」など
- BCPの重要性は「平常時から業務改善ができる」「「サプライチェーンとしての責任」「あらゆるステークホルダーへの社会的信頼の構築」「蓄電池による地域貢献」など
とくにこれからは、蓄電池による電源確保や地域貢献の重要性が求められるでしょう。BCP対策にとって蓄電池の存在は切り離せないでしょう。
監修

エコ発事務局 太陽光アドバイザー
曽山
『誠実、スピーディーな応対』をモットーに日々エコ発を運営しています。 お客様への応対だけでなく全国に数百ある提携業者様とのやり取りをはじめ、購入者様へのキャンペーン企画やウェブサイトの改善など、皆様のお役に立てるよう日々業務に取り組んでいます。 卒FIT後の太陽光発電の活用方法など、お困りごとがございましたら、お問い合わせにてお気軽にご相談下さい。
家庭用・産業用蓄電池の
無料一括見積もり