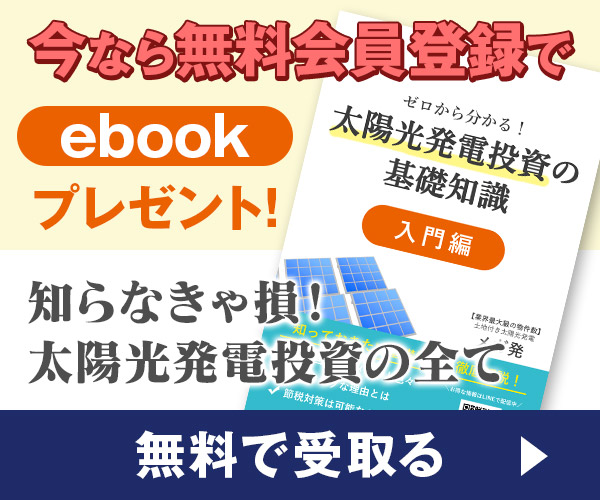蓄電池はどんな場所にでも設置できる?向き不向きはある?
公開日:2019/12/23 | | カテゴリ:蓄電池とは【基礎知識】

電気代が高騰していることにより、蓄電池への注目がさらに高まっています。
これまで太陽光発電は、蓄電池がなくてもFIT制度の恩恵を受けて売電収入によって十分な経済メリットがありました。しかし余剰買い取りのみになったことで、自家消費で使いきれなかった分の売電しか出来ず夜間は発電されない太陽光発電の特徴から、昼に使いきれなかった電力を溜めておいて夜間に利用出来る蓄電池が爆発的に売れだしました。
このように太陽光発電が売電から自家消費という価値シフトしていく流れの中で、蓄電池は太陽光発電と組み合わせることで余剰電力を売電せずに充電して、自家消費の利用量を増やしてくれる非常に重要なアイテムです。
とはいえ、蓄電池は太陽光電池とは設置条件や適した設置環境が異なります。そこで本記事では、蓄電池の設置方法やその手順、向き不向きなど設置に関連した押さえておくべきポイントを解説してきます。

蓄電池の設置方法3パターン
蓄電池を設置する方法は、基本的に次の3パターンがあります。
太陽光発電の設置時期との関係性によって、設置方法が異なります。まずはそれぞれのパターン別に、具体的なメリットや注意点などを見ていきましょう。
目次
新設の太陽光発電とセットで設置
太陽光発電を新規で設置する際に、同時に蓄電池も設置するパターンです。固定価格買取制度による売電ではなく、自家消費やZEH住宅の節電効果による経済メリットの受益を目的に蓄電池もセットで設置をします。
昼間に発電した余剰電気を売電せずに蓄電池へ充電して、太陽光発電が発電できない夜間や翌朝に放電して利用することで、電気を購入せずに節電効果を最大限に高めることができるのです。
電気代が高騰している現在では最もスタンダードなものと言えるでしょう。

いずれも新規で設置するため、蓄電池のメーカーや型式、容量等の仕様に制限が少なく、太陽光発電のメーカーや仕様に照らし合わせて、柔軟に組み合わせを比較検討して選択することができます。
加えて、蓄電池の配線や機器の配置も太陽光発電の設計に合わせて調整できるため、特に大きな問題もなく進めることができます。設置工事に関しても、太陽光発電を設置する業者もしくはその関係業者にお願いすることになるため、情報連携等がスムーズで工期どおりに設置が進むでしょう。
また、このパターンではハイブリッド蓄電システムという、太陽光発電と蓄電池のパワーコンディショナーを一体にしたタイプの蓄電システムを設置するのに非常に適しています。通常は、太陽光発電と蓄電池でそれぞれ1つずつパワーコンディショナーが必要になりますが、ハイブリッド蓄電池システムでは1台のパワーコンディショナーで両方の役割を担います。
パワーコンディショナーが一体になっているため配線や設置位置の調整が必要になりますが、同時に新設する場合であればそこを自由に調整可能です。ハイブリッド蓄電システムを利用することで、パワコン1台分の設置スペースを省略出来る上に充放電効率の高いシステムを構築することができます。
ハイブリッド蓄電システムは、創蓄連携システムと呼ばれることもあります。対して通常の家庭用蓄電池は、定置型蓄電池やスタンドアローン型蓄電池と言われます。
既設の太陽光発電に追加設置
FIT制度の終了に向けて、これから最も多くなるのがこの設置パターンでしょう。FIT制度の期間中は売電中心だった太陽光発電の利用スタイルを、FIT制度が期間満了を迎えるタイミングで蓄電池を追加設置して、自家消費中心のスタイルに変化させるのです。
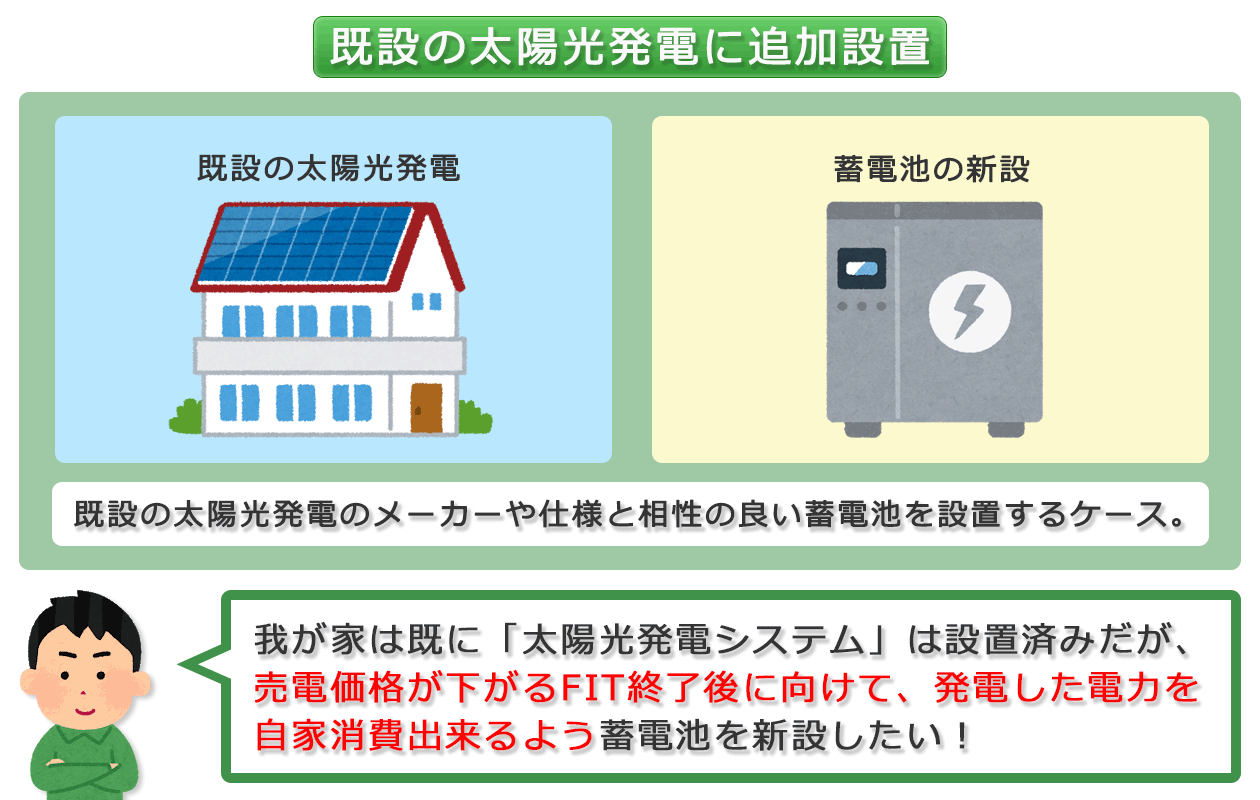
蓄電池の設置は、太陽光発電の設備や配線がすでに済んでいる状態なので、その位置関係に配慮した機器配置や配線の取り回しを検討する必要があります。また、住宅に設置する場合は、壁や分電盤の位置などを踏まえた形で設計していくことになります。
加えて、蓄電池のメーカーや仕様に関しても、太陽光発電のメーカーと互換性のある相性の良いものから選択しなければなりません。既設の太陽光発電のパワーコンディショナーの仕様によっては、蓄電池が設置できる仕様のものへの交換が必要になる場合もあります。
新設の部分で紹介したハイブリッド蓄電システムも、このパワーコンディショナーの置き換え需要に対応したものも多く出ています。このように、蓄電池メーカーもFIT制度終了後の設置が増えることを見越して、既設の太陽光発電に設置しやすい蓄電池を市場へ投入しています。そのため、蓄電池の仕様よりも設置に注意を払う比重に重きが置かれます。
太陽光発電と蓄電池併用に関して
【必見】太陽光発電と蓄電池はセットが当たり前!?
蓄電池単体で設置する
太陽光発電を設置していない・設置しない状態で、蓄電池のみを設置する場合もあるでしょう。太陽光発電を活用した売電や自家消費はできないものの、夜間に電力会社から安い電気で購入・充電しておいた昼間に利用することで、昼夜の電気代の価格差によって電気代の節約ができます。また、大規模災害など停電時の非常時の備えとしても、活躍が期待できます。

このパターンでは、太陽光発電の設備配置や配線を気にする必要がないので、蓄電池単体で最適な形で設置を進めることができます。 また、蓄電池の仕様に関しても、太陽光発電のメーカーや仕様に縛られることなく自由に決めることができます。
ただし、2024年現在では蓄電池の単体設置はあまりオススメ出来ません。その理由は以下の記事でまとめています。
蓄電池を導入するのは損でやめたほうが良い?必要性は?
蓄電池を導入するのは損でやめたほうが良い?必要性は?
蓄電池に特有な設置場所の向き・不向き
蓄電池は太陽光発電と同様に周囲環境の影響を受けやすい製品ですが、太陽光発電にはない蓄電池特有の設置場所の向き・不向きがあります。また、蓄電池は主に屋外設置のものが多く見られますが、メーカーによっては屋内設置のものもあります。
設置場所が蓄電池に適さない環境であれば、早期の劣化や重大な事故につながる恐れもあります。そこで、設置場所の向き・不向きについて、屋内外で共通する点、そして屋内設置・屋外設置それぞれに特徴的なポイントを解説していきます。
蓄電池に共通する適した設置場所

まずは屋内外に関わらず蓄電池に共通している設置場所に適した条件から見ていきましょう。特に重要なのが次の2つです。
広い設置スペース
蓄電池を設置する際には、ある程度広い設置スペースが必要です。これは、蓄電池が屋内外によらずサイズが大きいこと、そして蓄電池を設置したりメンテナンスする際の作業スペースを確保する必要があるためです。
特に屋外設置はサイズが大きく、蓄電池の本体とパワーコンディショナが1つの筐体になっているものであれば、エアコン室外機が縦に2つ積まれたくらいの大きさになります。住宅に設置する場合は、外壁に沿って設置されることが多くなります。このとき、隣の住宅との間に設置するのであれば、搬入時や作業時のスペース確保が厳しくなりがちなので注意が必要です。
また、屋内設置は屋外設置ほどのサイズはありませんが、空気清浄機くらいのコンパクトなものからエアコンの室外機程度のサイズになるものもあります。屋内に置かれる設備の中では、冷蔵庫や洗濯機に次ぐサイズのものなので、配線関係を考慮しつつ室内の中でどこに配置するかをよく検討しておくことをオススメします。
屋内外いずれの蓄電池も、メーカーから作業スペースを考慮した離隔距離が設定されていますので、そちらを遵守して設置しましょう。
設置エリアが寒冷地でない
蓄電池は、北海道など寒冷地エリアでの設置に向いていません。蓄電池の設置基準の1つに使用できる周囲温度が設定されていますが、ほとんどのメーカーが下限温度を-10℃もしくは-20℃としています。それ以下の温度では、満足に蓄電池の性能が発揮されないのです。
身近なところでわかりやすい例が、スマートフォンです。
実は蓄電池は、スマートフォンやパソコンに用いられているバッテリーと同じリチウムイオン蓄電池という種類のものを使っています。雪が降るような寒い日やスキー場では、スマートフォンにまだ電池残量があるにも関わらず電源が入らなくなる現象がありますよね。
このような現象が起こるのは、リチウムイオン電池が低温時に性能が低下してしまう特性を持っているためです。低温時に内部抵抗が大きくなって起電力が低下したり、また蓄電池の容量が小さくなるなど正常に蓄電池が機能せず、最終的には動作を停止してしまう場合もあります。そのため、寒冷地エリアに設置してしまうと、蓄電池が正常に動作しない可能性があるのです。メーカーによっては、北海道では販売自体を行っていないところもあります。
※最近は寒冷地仕様の蓄電池も増えています。
屋内設置の蓄電池に適した設置場所

次に屋内設置の蓄電池で、適した設置場所や注意すべきポイントを解説していきます。大きく次の3つがあります。
重量に耐えられる床
蓄電池は非常に重量の重たいものですので、その重量に耐えられる床に設置しなければなりません。重量はメーカーや型式、容量によっても大きく変わりますが、軽いものでも50kg以上で、重いものになると100kg〜150kgを超えるものもザラにあります。設置してすぐに問題がなかったとしても、数年ほど経ってから床材が座屈したり抜けてしまうかもしません。
そのため、設置前には床の耐荷重や床下に芯材が入っているかなどを調べたうえで、設置場所を決めましょう。また、蓄電池はその重量ゆえ簡単に移動したりもできませんので、設置場所は慎重に選ぶことをオススメします。
熱や湿気がこもらない環境
蓄電池は、低温もそうですが熱による高温や湿気も大敵です。そのため、設置場所として適度な換気がされて熱や湿気のこもらない環境を選ぶ必要があります。電池の内部温度が上昇してしまうと最悪の場合、発火や破裂する恐れがあります。
一時期、海外製のスマートフォンのリチウムイオンバッテリーが過剰に熱をもち、発火する危険性から機内持ち込みが禁止され、製品回収された例もありました。 もちろん蓄電池の設計は、熱を持たないような構造であったり、熱をもってしまっても発火したり燃え広がらないよう構造的な工夫や安全性を確認する試験がなされています。上記のスマートフォンの例は、設計不良による構造上の欠陥や製造工程の欠陥が原因でバッテリー自体に問題はありませんでしたが、蓄電池である以上は過熱状態になると発火などに発展することも考えられます。また、高温状態で利用を続けると、蓄電池の劣化も早くなってしまいます。
特に屋内設置の場合は、設置場所を確保できるのが階段下の物置きスペースやクローゼットの中など、換気が十分ではない密閉空間に設置してしまうことがあるので、注意が必要です。また、室内設置の蓄電池は脱衣所や洗面所への設置も多くなりがちですが、湿気が多いため蓄電池の設置場所には向いていません。
運転音が気にならない部屋
蓄電池はわずかではあるものの運転音がするため、寝室など音が気になる部屋への設置は避けるべきです。蓄電池も電気機器のため、運転音が出ることは避けられません。
ただ、メーカーや型式によりますが、蓄電池の運転音はおおむね35db〜40dbほどと小さいものです。これは、静かな図書館や昼間の閑静な住宅街などで感じる音の大きさとなっています。エアコンの室外機よりも運転音が小さいので、屋外設置の場合は気になるものではありません。また屋内設置であっても、普段生活している中ではほとんど気にならないレベルです。しかし、寝室や書斎など音に対して過敏になりそうな部屋には、設置しないほうが懸命でしょう。
屋外設置の蓄電池に適した設置場所
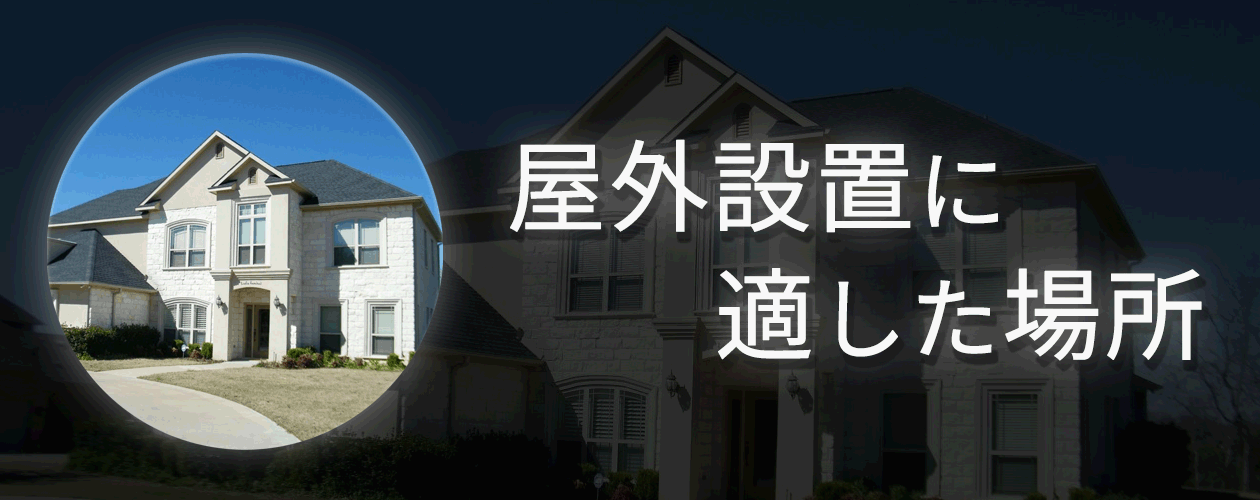
最後に屋外設置の蓄電池を設置するときに、適した場所や注意するポイントは次の3つがあります。
屋外設置ゆえ、周囲環境や自然災害の影響を受けにくい場所を選択する必要があります。具体的に配慮していくポイントを解説していきます。
直射日光が当たらない
蓄電池を屋外に設置する場合は、長時間の直射日光に当たらないよう配慮する必要があります。これは、直射日光が長時間当たると蓄電池が熱されて高温状態になってしまうためです。
上述したように、蓄電池は高温状態になると劣化の促進や発火等の事故原因となることもありえます。そのため、基本的にほとんどのメーカーで直射日光の当たる住宅の南面への設置は原則不可となっています。南面は避けて、東西面や北面など影になる位置に蓄電池を設置するようにしましょう。また、メーカーによってはオプション品として専用の日よけ板を用意している場合もあります。
この日よけ板を取り付けることで住宅南面へ設置できるようメーカーもあるので、どうしても設置場所を南面にせざるを得ない場合は、合わせて検討しましょう。
嵩上げして地面よりレベルが高い
蓄電池の設置場所は、浸水や水没を避けるためにコンクリート基礎を打って、嵩上げして地面から若干レベルの高い位置にする必要があります。電気機器である蓄電池は、水が大敵です。
太陽光発電のパワーコンディショナは壁面へ設置しますが、蓄電池はパワーコンディショナよりも重量が重いため壁面設置できません。基本的には地面設置になりますので、水没の影響を気にする必要が出てくるのです。
蓄電池が浸水したり水没してしまうと機器が故障してしまうのはもちろんのことながら、蓄電池の周辺へ近づいた人が誤って感電してしまうこともあり得ます。そのため浸水や水没の影響を受けないために、コンクリート基礎で地面から嵩上げを行わなければなりません。 また、コンクリート基礎を打つ理由の1つとして、地面が雨などで弱くなって自重で沈んでしまったり、地震によって倒れてしまわないよう固定して安定させるという側面もあります。
最近では、蓄電池の中にも壁面設置できるものが出てきているので、心配であればそういったタイプの蓄電池を選んでも良いでしょう。
塩害地域でない
電子部品の集合体である蓄電池は、塩害地域を避けて設置しなけれなりません。
塩害とは沿岸部のエリアに見られる現象で、海水に含まれる塩分によって機器内部の絶縁不良や金属等の構造物が腐食するといった悪影響を受けることをいいます。 塩害地域にもレベルがあり、潮風を受ける場所から海の波しぶきを直接受ける場所までさまざまです。
そのため蓄電池メーカーは、おおむね海岸線からの距離によって塩害地域・重塩害地域という形で区分けをして、設置可否を決めていることがほとんどです。ただ、瀬戸内海などの内海と、いわゆる普通の海に面した外海とで基準を分けている場合もあります。また、沖縄や離島は海岸線からの距離に関係なく、全域が重塩害地域に設定されているメーカーもあります。このように、海岸線からの距離と設置可否の関係性は、メーカーによって少しずつ違いますので、設置前に必ず確認するようにしましょう。
また、塩害地域であっても、住宅や倉庫などの建造物に守られて直接潮風が当たらなければ設置可能な場合もあります。また、蓄電池やパワーコンディショナ本体が塩害対策品のものや、オプション品として塩害部品をラインナップしているメーカーもあります。加えて、太陽光発電のパワーコンディショナでも塩害地域の設置基準がありますが、蓄電池は違うメーカーを使うときはその設置基準が異なりますので、注意が必要です。

正しく蓄電池を設置して効果的に自家消費
蓄電池は、FIT制度の終了による売電から自家消費へという太陽光発電のスタイルがシフトしていく中で、欠かせない製品です。太陽光発電との同時設置はもちろん、既設の太陽光発電への追加設置なども増えますが、その効果を十分に発揮するためには蓄電池に適した環境に設置する必要があります。
屋内設置と屋外設置で設置環境には向き不向きがありますし、誤った設置をしてしまうと劣化の早期化や効率の低下、火災等の事故につながることもあります。 蓄電池を利用して、より効率的に自家消費の節電効果を得るためにも、蓄電池の特性に合わせた正しい設置を行いましょう。
蓄電池の設置手順と費用について
蓄電池の設置手順と費用について
監修

エコ発事務局 太陽光アドバイザー
曽山
『誠実、スピーディーな応対』をモットーに日々エコ発を運営しています。 お客様への応対だけでなく全国に数百ある提携業者様とのやり取りをはじめ、購入者様へのキャンペーン企画やウェブサイトの改善など、皆様のお役に立てるよう日々業務に取り組んでいます。 卒FIT後の太陽光発電の活用方法など、お困りごとがございましたら、お問い合わせにてお気軽にご相談下さい。
家庭用・産業用蓄電池の
無料一括見積もり