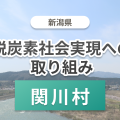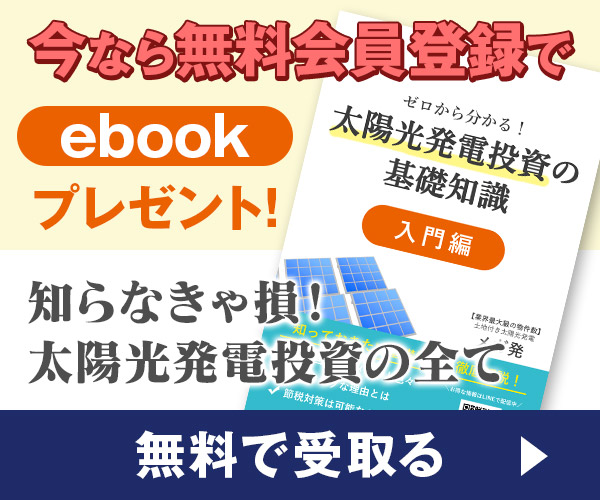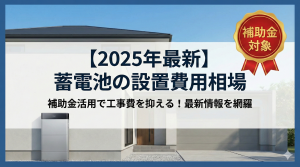【2026年】蓄電池の設置費用と相場!補助金で安く工事する方法
公開日:2019/12/23 | | カテゴリ:蓄電池とは【基礎知識】
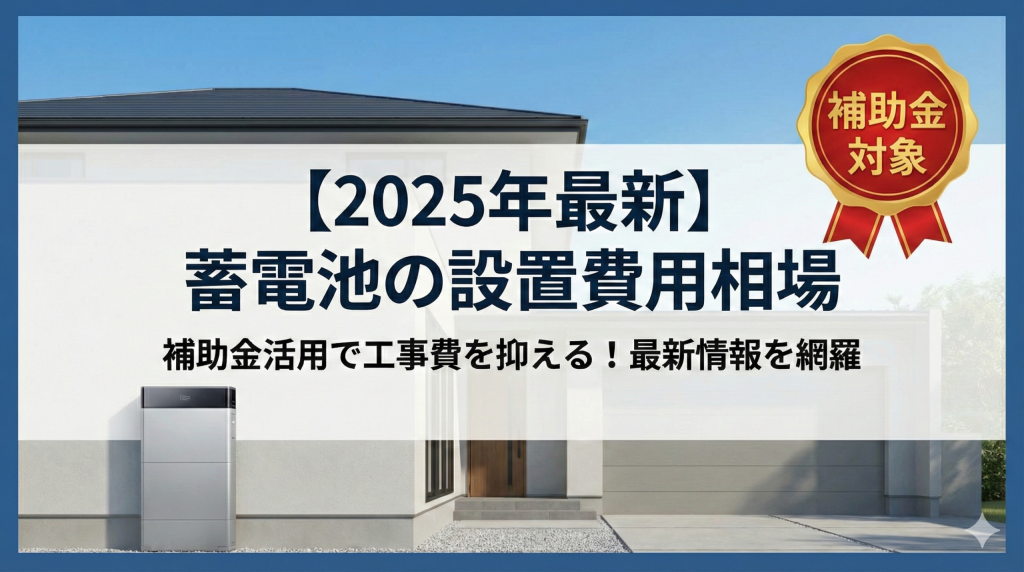
「自宅に蓄電池を設置したいけど、何から始めればいいんだろう?」
「工事って大変そうだし、費用も高そう…」
電気代の高騰や相次ぐ自然災害への備えとして、住宅用蓄電池への関心が高まっています。しかし、いざ設置を考えると、費用や工事内容、業者選びなど、分からないことだらけで一歩踏み出せない方も多いのではないでしょうか。
この記事では、そんなあなたに家庭用蓄電池の設置について、2026年1月現在の最新情報と押さえておくべきポイントを解説します。
- 蓄電池の設置にかかるリアルな費用相場(本体+工事費)
- 相談から完了までの具体的な蓄電池の設置工事の流れと期間
- 後悔しないための蓄電池の設置場所の選び方と条件
- 使える蓄電池の補助金の種類と賢い活用法
- 信頼できる蓄電池の設置業者を見抜く5つのチェックポイント
「蓄電池を設置してから後悔した…」とならないために、設置検討している方はぜひ最後までご覧ください。
家庭用蓄電池の設置で後悔しないための3つの最重要ポイント
蓄電池の設置で後悔しないために最も重要な3つのポイントを先にお伝えします。
- 蓄電池を設置する目的を明確にする
「電気代を節約したいのか」「災害時の備えを万全にしたいのか」で、選ぶべき蓄電池の容量や機能、価格は大きく変わります。目的が曖昧なままだと、オーバースペックで高価な製品を選んでしまったり、いざという時に容量が足りなかったりする原因になります。 - 蓄電池の設置費用は「総額」で判断する
見積書では、蓄電池の機器代を安く見せて工事費を高くするなど、販売施工会社側で内訳の調整が可能です。工事費だけを見て「安い!」とその販売施工会社に飛びつくのは危険。必ず複数の業者から相見積もりを取り、機器代と工事費を合わせた「設置費用の総額」で比較検討しましょう。 - 使える蓄電池の補助金制度は最大限に利用する
国や地方自治体から、数十万円~数百万円単位の補助金が受けられる場合があります。しかし、蓄電池の補助金は事前に予算額が決まっており、条件や申請のタイミングによっては補助金が受け取れないことも「どんな補助金があるか」「いつまでに申請が必要か」「補助金の条件を満たしているか」を事前に把握し、条件を満たした蓄電池を設置することで初期費用を費用を抑えることができます。
それでは、蓄電池設置のための3つのポイントをを詳しく見ていきましょう。
家庭用蓄電池の設置費用はいくら?費用総額と内訳を徹底解説
家庭用蓄電池の導入には機器本体の価格と施工会社による設置工事の費用がかかります。
【2026年最新】家庭用蓄電池の導入費用相場(本体+工事費)
設置工事費を含めた家庭用蓄電池の導入費用総額はおおよそ蓄電容量1kWhあたり約15万円〜20万円が目安です。一般家庭で人気の蓄電池の容量4kWh〜12kWhの容量帯で見ると、総額で約80万円〜220万円程度が相場となります。
蓄電容量が1~14kWhの場合、設置工事費を含めた費用は48.4万円~216.1万円とされています。
| 蓄電容量 | 設置費用の総額(工事費込み) | こんなご家庭におすすめ |
|---|---|---|
| 4~5kWh | 80万円~120万円 | ・夫婦2人暮らしなど電力使用量が比較的少ない ・日中の電気を少し賄えれば良い |
| 6~8kWh | 110万円~160万円 | ・3~4人家族の標準的なご家庭 ・日中の電気をほぼ賄いたい |
| 9~12kWh | 140万円~220万円 | ・5人以上の大家族や二世帯住宅 ・停電時にエアコンなども長時間使いたい |

設置費用の内訳①:蓄電池本体・関連機器の価格

蓄電池の設置費用の総額の大部分を占めるのが、蓄電池本体と、電気の流れを制御する「パワーコンディショナ(パワコン)」の費用です。特に蓄電池本体は、電気を貯められる容量(kWh)が大きくなるほど価格が高くなります。
- 蓄電池ユニット:電気を貯めるバッテリー部分
- パワーコンディショナ:太陽光や蓄電池の電気(直流)を家庭で使える電気(交流)に変換する重要な機器。すでに太陽光発電を設置している場合、既存のパワコンと連携できる「単機能型」か、太陽光用と蓄電池用を一つにまとめた「ハイブリッド型」かを選びます。
費用の内訳②:設置の工事費用

蓄電池の設置工事にかかる費用は、約30万円〜40万円が相場です。
工事内容は主に以下の3つで構成されます。
- 基礎工事:蓄電池を設置する地面をコンクリートで固める工事。
- 機器設置工事:蓄電池本体やパワコンを運び込み、固定する工事。
- 電気配線工事:蓄電池、パワコン、分電盤などをケーブルで繋ぐ専門的な工事。
設置場所の状況によっては、重機(クレーンなど)が必要になり、追加費用が発生する場合もあります。
注意!見積は「設置費用の総額」で比較しないと損をする理由
複数の施工販売業者から蓄電池設置の見積もりを取る際工事費の安さだけで判断してはいけません。
悪質な業者の中には、工事費用を極端に安く見せかけ、その分を機器本体の価格に上乗せして、総額では他社より高くなっているケースがあります。見積もり項目は施工販売業者が自由に設定できるため、このような価格操作が可能なのです。
必ず複数の業者から見積もりを取り、「機器代+工事費」の総額で冷静に比較することが、損をしないための鉄則です。

蓄電池の設置工事の流れと期間
「蓄電池の設置工事には何日もかかるのでは?」と心配される方もいますが、工事自体は約1〜2日で完了します。ただし、設置の相談を開始してから実際に設置が完了するまでには、全体で1〜3ヶ月ほどかかります。
相談から蓄電池設置完了までの全体像(1〜3ヶ月)
- 問い合わせ・見積もり依頼:まずは専門業者に相談します。
- 専門業者からのヒアリング:現在の電気使用量や設置目的などを伝えます。
- 現地調査:業者が自宅を訪問し、設置場所や分電盤の位置、搬入経路などを詳細に確認します。この調査が不十分だと後から追加費用が発生する可能性もあるため、丁寧に対応してくれる業者を選びましょう。
- 見積もり・プラン提案:現地での調査結果に基づき、最適な蓄電池の機種と正式な見積もり金額が提示されます
- 契約:内容に納得できれば契約を結びます
- 補助金申請:契約後、業者が国や自治体への補助金申請を代行してくれるのが一般的です
- 工事日程の調整:補助金の交付決定後、具体的な工事日を決めます
- 設置工事(1〜2日):当日は現地立ち会いが必要です
- 電力会社への申請・連携:系統連系など電力会社との手続きも業者が進めてくれます
- 引き渡し・運転開始:すべての工事と手続きが完了したら、操作説明を受けて利用開始です。
工事当日の具体的な3ステップ(1〜2日)
工事当日は、主に「基礎工事」「機器設置・配線工事」「設定・試運転」の3つのステップで進みます。
ステップ1:基礎工事
屋外に設置する場合、蓄電池ユニットを置くためのコンクリート基礎を作ります。コンクリートが固まるのに数日かかるため、事前にこの作業だけ行うことも。最近では、工事が1日で完了する「簡易基礎(置き基礎)」に対応した蓄電池も増えています。
ステップ2:機器設置と配線工事
基礎の上に蓄電池ユニットやパワコンを設置し分電盤などとケーブルで接続します。壁に配線用の穴を開ける作業があり工事中で最も大きな音が出ることがあります。
ステップ3:設定・試運転と引き渡し
すべての機器を接続したら、初期設定と試運転を行い、問題なく作動することを確認します。最後に業者から使い方や保証に関する説明を受け工事は完了です。
工事中の注意点:停電と騒音に備えよう
設置工事中必ず1〜2時間程度の停電が発生します。これは、ご家庭の分電盤に蓄電池システムを接続するための作業です。
- 冷蔵庫:2〜3時間程度であればドアを開閉しなければ保冷は保たれます。
- パソコン・ネット機器:事前に電源を落とし、作業が完了してから再接続しましょう。
- エアコン:故障を防ぐため、事前に電源を切っておくことが推奨されます。
工事担当者から事前に停電の時間帯について案内があるので心の準備をしておきましょう。
どこに置く?蓄電池の設置場所と満たすべき条件
蓄電池はどこにでも置けるわけではありません。安全性や性能を維持するために、いくつかの条件を満たす必要があります。主な設置場所は「屋外の外壁」と「屋内」です。
屋外設置のメリット・デメリットと注意点
最も一般的な設置方法です。
- メリット:家の中のスペースを圧迫しない。運転音が気にならない。
- デメリット:直射日光や雨風にさらされる。塩害や積雪の多い地域では対策が必要。
- 注意点:高温・多湿を避ける。浸水を防ぐため、しっかりとした高さのある基礎の上に設置する。メーカーが定める離隔距離(他の物との距離)を確保する。
屋内設置のメリット・デメリットと注意点
塩害地域や豪雪地帯で選ばれることが多い方法です。
- メリット:天候の影響を受けにくく、劣化を抑えられる。
- デメリット:設置スペースの確保が必要。機種によっては運転音が気になる場合がある。重量があるため床の補強工事が必要になることも。
- 注意点:高温多湿にならない、換気の良い場所を選ぶ。消防法により、設置できる容量や場所(居住スペースは不可など)に規定があります。
どちらが良いかはご自宅の環境によります。現地調査の際に施工業者としっかり相談して場所を決めましょう。
最大数十万円~数百万円の蓄電池の設置で使える補助金制度(2026年最新情報)
高価な蓄電池ですが、国や自治体の補助金を活用することで、初期費用を大幅に抑えることができます。
国からの蓄電池の補助金

国は、再生可能エネルギーの普及を目的として、蓄電池導入に関する補助金事業を毎年実施しています。
過去には以下のような事業がありました。(※2025年度の事業は最新情報をご確認ください)
- DR補助金(電力需給ひっ迫等に活用可能な家庭・業務産業用蓄電システム導入支援事業)
- 子育てエコホーム支援事業(ZEH住宅に関連する補助)
これらの補助金は予算が上限に達し次第、受付が終了してしまいます。検討している方は、早めに情報収集を開始し、補助金申請に詳しい業者に相談しましょう。
地方自治体(都道府県・市区町村)からの補助金

国とは別に、お住まいの地方自治体が独自に補助金制度を設けている場合があります。東京都の「災害にも強く健康にも資する断熱・太陽光住宅普及拡大事業」のように、非常に手厚い補助が受けられるケースも。
補助金に詳しい業者に確認してもらいましょう。国と地方自治体の補助金は併用できる場合も多いので、必ずチェックしてください。
蓄電池の補助金申請をスムーズに進めるコツ
補助金の申請は手続きが複雑で、必要書類も多岐にわたりますが、申請は施工販売業者が代行してくれるケースがほとんどです。
ほとんどの場合、設置業者が申請手続きを代行してくれます。
そのため、業者を選ぶ際には「蓄電池の補助金の申請実績が豊富か」「最新の補助金情報に詳しいか」といった点も重要なチェックポイントになります。
家庭用蓄電池を設置するメリットは?
蓄電池を設置するメリットを「目的別」にお伝えします。ご自身の目的と照らし合わせることで、導入の価値がより明確になります。
メリット1:電気代を節約できる(経済性重視の方へ)
電気料金プランを夜間の電気代が安いプランに変更するのがポイントです。
- 太陽光発電がある場合:昼間に発電した電気を蓄電池に貯め、夕方〜夜間に使うことで、電力会社から電気を買う量を最小限に抑えます(自家消費)。
- 太陽光発電がない場合:電気代の安い深夜電力を蓄電池に貯め、電気代の高い昼間に使うことで、差額分だけ電気代を節約できます。
特に、太陽光発電の余剰電力を固定価格で買い取ってもらう「FIT制度」が終了したご家庭(卒FIT)では、売電するより自家消費した方が経済的メリットは大きくなります。
メリット2:停電・災害時でも電気が使える(安心重視の方へ)
地震や台風による大規模な停電が発生しても、蓄電池に貯めた電気で普段と近い生活を送ることができます。
- 情報収集:テレビやスマホで最新の情報を得られます。
- 食事の準備:冷蔵庫やIHクッキングヒーター、電子レンジが使えます。
- 快適な環境:エアコンや照明が使え、避難生活のストレスを大幅に軽減できます。
太陽光発電と組み合わせれば、停電が長引いても日中に発電・充電できるため、もしもの時も安心です。
メリット3:EV自動車を蓄電池としても活用できる(V2H)
電気自動車(EV)をお持ち、または購入予定の方には「V2H(Vehicle to Home)」という選択肢もあります。
V2Hシステムを導入すれば、EVの持つ大容量バッテリー(一般的な家庭用蓄電池の数倍)を、家庭用の蓄電池として利用できます。これにより、停電時には家全体の電力を数日間にわたって賄うことも可能になります。
蓄電池の設置業者を選びに失敗しない5つのチェックポイント
蓄電池の導入が成功するかどうかは、業者選びが重要です。以下の5つのポイントを必ずチェックしましょう。
- 施工実績は豊富か?
蓄電池の設置には専門的な知識と技術が必要です。公式サイトで施工事例などを確認し、実績が豊富な業者を選びましょう。 - 複数のメーカー製品を取り扱っているか?
特定のメーカーしか扱っていない場合、そのメーカーの製品しか施工会社からは提案されません。複数のメーカーを比較検討し、あなたの家に最適な蓄電池機器を提案してくれる選択肢の多い施工会社がおすすめです。 - 現地調査を丁寧に行ってくれるか?
見積もり前の現地調査は重要です。設置場所の寸法を測るだけでなく、分電盤の状況、配線のルート、日当たりや周辺環境まで細かくチェックし、設置する際のリスクを説明してくれる業者は信頼できます。 - 見積もりの内訳が明確で、総額が適正か?
前述の通り、見積もりは必ず「総額」で比較しましょう。「一式」などの曖昧な項目がなく、内訳でいくらかかるのかが明記されているかを確認してください。 - 補助金申請やアフターサポートの体制があるか?
面倒な蓄電池の補助金申請をサポートしてくれるか、設置後の保証や万が一のトラブル時に迅速に対応してくれるかどうかも、長く安心して使うための重要なポイントです。
蓄電池の設置に関するよくある質問(Q&A)
最後に、蓄電池の設置に関してよく寄せられる質問にお答えします。
Q1. 設置後のメンテナンス費用はかかりますか?
A1. 基本的に、家庭用リチウムイオン蓄電池は定期的なメンテナンスは不要です。ただし、長期間安心して使うために、メーカー保証の内容(通常10〜15年)は確認しておきましょう。メーカー推奨外の使い方をすると保証対象外となり、高額な修理費がかかる可能性があるので注意が必要です。
Q2. 太陽光発電がなくても設置する意味はありますか?
A2. はい、意味はあります。 電気代の安い深夜電力を貯めて昼間に使うことで電気代を節約できますし、何より災害時の非常用電源としての価値は非常に大きいです。ただし、太陽光発電と組み合わせた方が、経済的なメリットも防災面のメリットも最大化できます。
Q3. 設置に必要な届出は自分で行うのですか?
A3. 消防法に基づき、一定の容量を超える蓄電池を設置する際には消防署への届出が必要になる場合があります。しかし、これらの法的な手続きは、通常は設置業者が代行してくれますので、ご自身で何かをする必要はほとんどありません。
まとめ:信頼できる専門家と、後悔のない蓄電池ライフを
家庭用蓄電池の設置は、決して安い買い物ではありません。しかし蓄電池を設置することで電気代の削減だけでなく、災害時の非常電力としても安心です。
後悔しない蓄電池設置のポイント
- 目的を明確に:節約か、防災かで最適な製品選びに必要。
- 費用は総額で:見積もりは複数社から取り、工事費だけでなく総額で比較しましょう。
- 工事は1〜2日:実際の設置の流れと注意点を把握しておけば安心。
- 補助金を活用:国と自治体の制度を調べ、申請に強い業者を選びましょう。
- 業者選びは慎重に:実績、サポート体制をしっかり見極める。
まずは信頼できる蓄電池設置の専門業者に相談し、あなたの家に最適なプランの提案を受けてみてはいかがでしょうか。一括見積もりなら最大5社から最適な業者がわかります。たった、60秒で完了で複数業者との面倒なやり取りも一切ないので、ぜひ利用してみてください。

監修

エコ発事務局 太陽光アドバイザー
曽山
『誠実、スピーディーな応対』をモットーに日々エコ発を運営しています。 お客様への応対だけでなく全国に数百ある提携業者様とのやり取りをはじめ、購入者様へのキャンペーン企画やウェブサイトの改善など、皆様のお役に立てるよう日々業務に取り組んでいます。 卒FIT後の太陽光発電の活用方法など、お困りごとがございましたら、お問い合わせにてお気軽にご相談下さい。
家庭用・産業用蓄電池の
無料一括見積もり